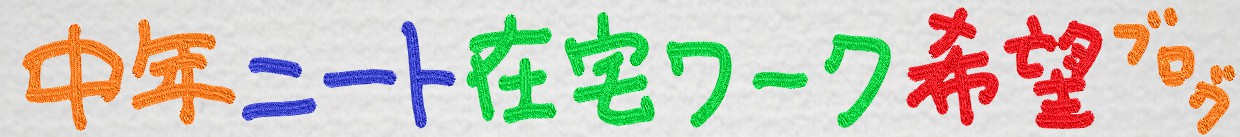(
kinkateによる
Pixabayからの画像)
発達障害当事者の感覚って、定型者(普通の人)にとってはかなり分かりにくいのではないでしょうか。
精神科医でさえ発達障害独特の感覚、感性を深く把握して診断できる方は少ないと思います。
一応現在主流の診断基準に沿って診断をするのでしょうが、要は該当するか当てはめてチェックしているだけなので、 症状の強い患者でさえも「異常なし」「グレーゾーン」と診断されるケースもあるでしょう。
数時間の問診やテストが必要不可決なのに、1回目の外来であっけなく診断されてしまうこともあるようです。
そういう現状なので、
とヘコむ必要はありません。
まだまだ発達障害の認知や研究は過渡期なので、今後も見解や診断基準が変わっていく可能性は大いに考えられます。
結局は、診断されたら解決するわけではないです。
やっとスタートラインに立ったようなものです。
「発達障害持ち」という前提で苦手な事を克服、回避、フォローしてもらい、得意な事に特化していけるきっかけを得たに過ぎないわけです。
そこからは深い自己分析が必要になってきます。
定型者との感覚差や、自分が著しく苦手な事を具体的に把握する必要があります。
これらの意見は僕個人の見解ですが、定型者側が発達障害への認知を広げてくれるのを待つだけでは生き辛さを克服できないと思っています。
当事者自身が自分の特性を深く理解し、定型者に少しでも共感してもらえるように行動していかなければいけません。
当ブログもそういったコンセプトで記事作りしています。
という事で前置きが長くなりましたが、定型者と発達障害者の感覚差を『山登り』に例えてイメージしてみました。
自分で言うのもなんですが、感覚の再現度は結構高いと思います。
 |
会話時

(
coahnによる
Pixabayからの画像)
定型者は秋の行楽シーズン、枯れ葉の積み重なったフカフカの山道の様に、心地よく歩ける。
風景(相手とのコミュニケーション)を楽しめる。
当事者は、例えば左足側(話の内容)が砂利で、右足側(相手の表情)が尖った岩の山道を歩く感覚。
常に緊張状態で、左右を常にチェックしながら歩かないといけないので、神経がすり減る。
ロープや手摺りがないケース(初めて会う人、普段あまり話さない相手)だと、さらにきつくなる。
立ち止まったり、つまづいて転んでケガをしてしまう事も多い。
当然、風景を楽しむ余裕など持てない。
車の運転で言えば、自動運転とF1くらいの差があるかも。
車の運転で言えば、自動運転とF1くらいの差があるかも。
発達障害者、特にASDは話を文字通りに受け取る傾向があるといわれますが、 よくよく考えたら相手の表情を見つつ話を聞くという事ができないせいかもしれません。
…そうホザく僕も、前回と今回の記事を書いていてようやく
と理解できたレベルです(汗)
目次に戻る
-
Googleアドセンス広告
-
作業時

(
Free-Photosによる
Pixabayからの画像)
仕事で指示された事をやる時、小中学生の授業中の課題で共同作業をやる時など。
定型者は、手摺りのある階段を昇る感じ。
場所(作業内容)により長短や勾配差(時間・難易度)はあるものの、疲れるが普通に頑張れば上れない事はない。
集団で上る時も前後適切な感覚を取り、周りに合わせて一定のペースで進んでいける。
集団で上る時も前後適切な感覚を取り、周りに合わせて一定のペースで進んでいける。
当事者の場合、1段の高さが50㎝位ある上に幅が狭く、はしご並みの絶壁階段となる。
手摺りもないので上るのが大変。踏み外すことも多い。前後の感覚の取り方も難しい。
ていうか、上る事さえできなかったりする。
ていうか、上る事さえできなかったりする。
でも周りの定型者からは
としか映らない。
そうこうしているうちにどんどん遅れていってしまう。
一人だけ取り残される疎外感は大変辛いものがある。
…山が例えじゃなかったですね(汗)
僕の体験談を書いた記事がありますので、読んでみてください。
目次に戻る
-
就労移行支援の広告
【atGPジョブトレ 発達障害コース】

・発達障害専門の就労移行支援事業所
・発達障害の方に合わせたトレーニング
・自分の障害や対策への理解を深められる
-
【atGPジョブトレ IT・Web】

・Web制作と勤続スキルを均等に習得
・未経験でもWeb制作スキル習得が可能
・就職活動や就職後もサポート
慣れた作業&過集中時

(
Gill Cooperによる
Pixabayからの画像)
誰でも作業がはかどりだして熱中する事はあると思いますが、当事者の場合それが常軌を逸したものになります。
普通どんなに集中していても、疲れが出たら休憩を取ります。
しかし発達障害当事者はその感覚が鈍かったりします。
どんなに疲れてもゲーム依存症のごとく作業をやめられなくなります。
いわゆる「過集中」状態になり、疲れの感覚を感じなくなってしまう事があります。
ひたすら全力を出し続けて作業をします。
自分に対し一切の妥協を許しません。
自分に対し一切の妥協を許しません。
周りは
と声掛けしたりします。
それでもやめずに続ける人が多いと思います。
定型者が平地を100メートルダッシュする中、当事者だけ下り坂で猛ダッシュしてスピードアップし、 止まれなくなっている状態だと見れば分かりやすいでしょう。
当然、その後のダメージと疲労はすさまじいものになります。
まさに「後先考えない」行為です。
ちなみに僕は小さい頃からずっとこんな感じなので、やる日とやらない日の落差が激しいです。
ほどほどの集中力、一定のペースで進行する事ができないのです。
そういった意味では他人の管理下で作業をしたほうがいいのかもしれません。
…これも山関係なかった(汗)
以上になります。
今回は発達障害当事者の「独特な感覚」を理解してもらいたく思い、記事にしてみました。
と感じてしまった方は、普通じゃないと思いますので、色々発達障害や自分の特徴について調べてみましょう(笑)
目次に戻る
広告
リンク
広告
リンク