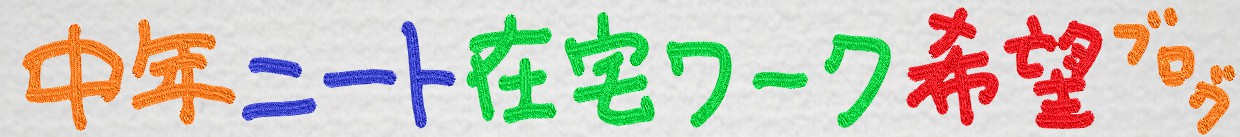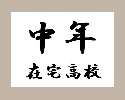柔道技解説第4弾。「大内刈り」を解説します。
柔道経験者ならやらない人はいない、地味ながらも一番使われている技です。
背負い投げ・体落とし・大外刈りが「大技」ならば、大内刈りは「小技」と呼ばれたりします。
「大技」とは決め技、「小技」は大技に行くための崩し技のような扱いになります。
ちなみに、すぎひろが最も得意とする技ですので、熱意圧が高い説明になるかもしれませんが、ご了承願います!
 |
技の掛け方
手順
ここでは右組手で説明します。左の人はそのまま反転してください。①右自護体で組み、左側による

②相手の両足の手前、両足幅の中央あたりに右足を踏み込む
・膝を曲げて少ししゃがむ
・指先は右斜め向きにする。踵(かかと)は浮かせた状態。

③続いて左足先を右足の土踏まず辺りにややずらして踏み込む
・踵は浮かす。
・引き手と釣り手を自分の胸にギュッと絞るように寄せる。
女性が巨乳アピールするような両腕の形をイメージ。(セクハラ表現ですみません!)
・頭を相手の胸につきそうなくらい寄せる、目線は、相手の左足先に向ける。
・つま先立ちで相手にほぼ密着してしゃがむので、重心が後ろに行きそうになるが、そこは両腕を絞ることでカバー。

④右足つま先を相手の両足の間に通す
・膝からつま先まで一直線に伸ばす
・足裏1つ分相手の左足スレスレの位置に差し込む

⑤右膝からつま先を反時計回りに90°ひねり、自分の足首から脹脛(ふくらはぎ)の間で、 相手の左脚の同じ所を草刈り鎌でサクッと刈るように叩く

⑥すると相手の左脚が少しずれるので、相手の股を裂いて広げ、尻もちをつかせるイメージで、 自分の右足を前に踏み出しながらコンパスで円を書く様に時計回りに動かす
・右足は90°ひねったままで回す。親指先を畳にスレスレに擦るように動かす。
・膝は曲げ過ぎずに、右脚全体が緩やかにカーブしているイメージ。
・膝からつま先まで真っ直ぐにすると、踵から足首部分がフックの様に突き出る。
この踵で相手の足首から踵を引っ掛けて股裂きにしていく。
・同時に絞っていた釣り手を下に突き出し、右足を追うように落としていく。

その際少し手首を反時計回りに捻(ひね)って、手の肚の部分で押していくと力が伝わりやすい。
⑦自分も一緒に倒れ込むイメージで倒す。最後まで釣り手を相手の胸に突き押す。
・最終的に右腕が伸び切るようにする
・結果的に右後方まで体が動くイメージで
・引き手は終始絞ったまま。肘は横っ腹に着けっぱなし。

目次に戻る
ポイント
○懐にしゃがんで踏み込む事で相手の重心を右足1本に集中させ、そこを刈って倒す○引き付けて密着し、相手を逃がさないようにする
○相手の脚を叩いたら、股を割いて広げるように自分の脚も伸ばしていって半円を書いていくイメージ
注意点
○引き手と釣り手を絞る際に、自分の重心が後ろに行かないよう注意!○最初の踏み込みで右足指先が左方向に向いていると、足を刈る際に背中がのけぞる体勢になりやすいので、 「大内刈り返し」で逆に投げられてしまう事も
 |
 |
 |
○軸足の足裏がベタ付きだと、踵が床に引っ掛かり、体が回転していかない

○引き手と釣り手を絞らないで足を掛けると、簡単に足を上げられて躱されてしまう
 |
 |
 |
目次に戻る
練習方法
○打ち込みで手順を1つ1つ確認しながらゆっくりやってみる○形を覚えたら、少しずつスピードを上げてみる
○打ち込み時は、右足を差し入れる所までか、軽く足首上を叩くところまでやる
○型を安定させたい、またはスピードを上げたいのであれば、踏み込み迄の打ち込みでも可
○投げる時、脚の動作は刈る前よりも刈った後の動作を大きくする。
本当は投げるまでやるといいのだが、いちいち投げていたら相手が苦しいし、時間も掛かるので遠慮がちで!
○打ち込みの最後の1回で投げてみる
釣り手のより良い使い方
ただ絞るだけでなく、一旦相手を自分側に引き出してから、 相手の左鎖骨から肩辺りに拳の肚を押し当てる動作を取る。拳は半円を書くイメージで動かし、押し当てる直前に反時計回りにひねり、拳の肚で押せる形にする。
これが出来ると、より相手の重心が左脚に集まるので、脚を刈った時の「草刈り鎌スッパリ」具合も増す。
 |
 |
 |
1人で練習してみる
相手の足の位置を想定し、踏み込みから足を掛けて倒れ込む所までやってみる。最終的に180°回転して前受け身を取るまでやる。
写真やGIF動画ではスペースの問題上、腰が引けた状態になっていますが、慣れないうちはこれでもOK!
(インソールは別に置かなくてもいいです!)

禁止技
足取り大内
相手の膝から下あたりを掴むか抱え、残りの足を刈る。 |
 |
 |
現状のルールでは直接下半身を手で掴みに行く行為は反則になってしまう。
流れで、たまたま足に触れたり手を添える形ならば問題ないらしい。(曖昧ですみません!)
ちなみに、これも僕の得意技だったので残念!
河津(かわづ)掛け
蛇の様に足を絡める行為。 |
 |
 |
「蟹挟(かにばさ)み」と同じく、ケガのリスクが高いので禁止技に。
目次に戻る
Googleアドセンス広告
連絡変化
単発で技に入っても、なかなか相手を投げられません。
技と技を連携させて攻める事を「連絡変化」といいます。
詳しくは以下の記事を読んでみてください。
 【柔道実践マスターシリーズ=連絡変化=】
【柔道実践マスターシリーズ=連絡変化=】立ち技で相手を投げるためには、自分が技に入りやすい組み手に持っていく、相手を崩してから入る、連続で技を掛けて投げる… 【柔道実践マスターシリーズ=連絡変化=】
ハ方崩し(前)→大内刈り(後ろ)
 |
 |
 |
相手をあおり、手前に引き上げたところに技を掛ける。
支え釣り込み足(右前)→大内刈り(右後ろ)
 |
 |
 |
右に崩して相手を左に動かし、その流れで足を床に着かずに相手の左脚を刈る。
目次に戻る
内股(前)→大内刈り(後ろ)
 |
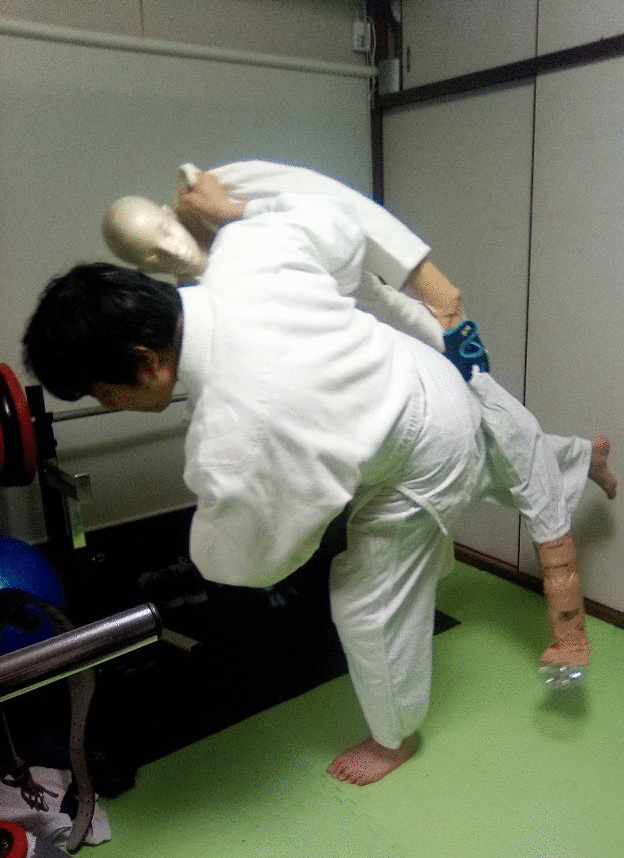 |
 |
相手の股ぐらに差し入れた足を使い、そのままの流れで反転して刈る。
小内刈り(左後ろ)→大内刈り(右後ろ)
 |
 |
 |
小内刈りで左後方に崩し、相手が体制を立て直そうと右脚に重心を移動する所を狙う。
背負い投げ(前)→大内刈り(後ろ)
 |
 |
 |
背負い投げで決めきれない時、またはフェイントとして背負い投げを掛けた後、振り向き様に相手の左脚を刈る。
割とポピュラーな連絡変化。最初にしゃがんで踏み込んでいるし、技から戻る動作をそのまま利用できるため掛けやすい。
目次に戻る
-
サプリメントの広告
【カツサプ】

・カツオ・ペプチド配合の運動補助食品。
・アミノ酸が2個つながった構造。
・血中乳酸の分解、筋肉疲労回復を目指す。
-
Googleアドセンス広告
応用
奥襟をつかんで掛ける
 |
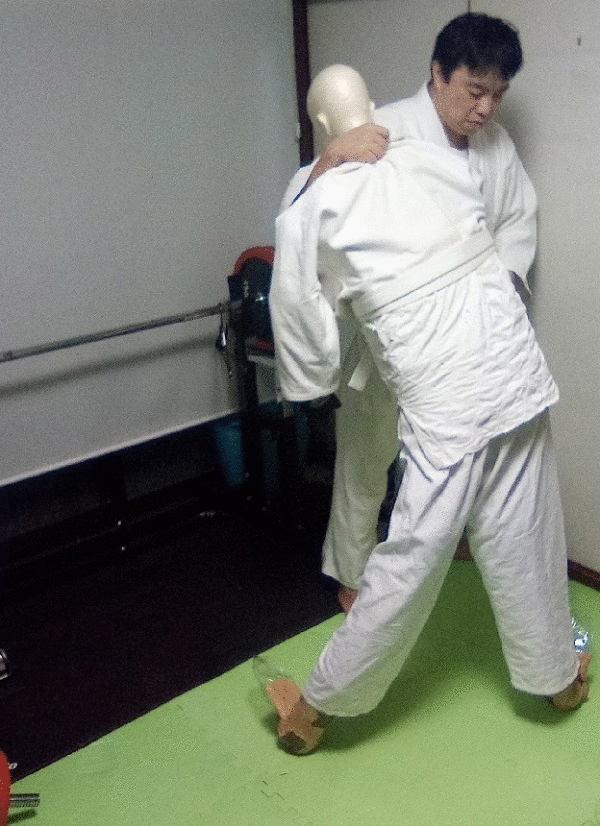 |
 |
足を引っ掛けて体を預けて倒れ込む形。
釣り手の崩しをやる際、相手の体を押すことが出来ないので、同じ型の崩しをしつつ代わりに相手襟首を後方に押していく。
ケンカの際、不良が相手の襟首をつかんで引っ張り倒すようなイメージ。(実際にはやらないでください!)
モデル級美女で有名な、女子48kg以下級の世界王者ダリア・ビロディド選手(ウクライナ代表)(参考:ウィキペディア)の得意技。
172㎝もあり、同階級の選手よりかなり身長が高いので、こういった掛け方をしている様。
足を引っ掛けて刈る
 |
 |
 |
むしろこのやり方が主流かも。
膝を曲げた状態で、足首から脹脛(ふくらはぎ)辺りで相手の同じ部分を刈る。
足の動きは小さいが、上半身の崩しがしっかりしていれば十分有効。
ケンケン移動して体制を整えて倒すやり方も多い。
但し踏み込みが浅く、遠目から技を掛けた場合、返されるリスクがあるので注意。
最初に踏み込んだ足先も左向きになっていると、簡単に返されやすい。
低い位置から技を掛ける

軽量級に多い傾向だけど、お互いに前傾姿勢で組み手争いをしている中、 膝が着くか着かないかの低い位置から大きく踏み込んで相手の足を刈っていく。
一気にもも辺りまで、相手の股の間に入れ込んでいくイメージ。
自分の膝で相手の踵を引っ掛ける感じ。
足を大きく回していった方が効果的。当然上半身の崩しが肝!
腹筋と足腰の強さがないと、なかなか出来ないかも。
目次に戻る
以上です。僕の説明したやり方は、師匠である町道場の先生から教わったものです。
それから自分なりに追究してこの形を作りました。
マスターできれば、切れ味・威力共に絶品なので、是非練習してみてください。
この技だけは、自信あります!
PS.
柔道着、サポーターなどのグッズを紹介した記事も書いていますので、ぜひ一読を!
柔道着、サポーターなどのグッズを紹介した記事も書いていますので、ぜひ一読を!
広告
リンク
【柔道部物語】
アラフォー以上の柔道経験者のバイブル漫画。
すぎひろが中高生の時に連載。
かの五輪3連覇の 野村忠宏七段(参考:ウィキペディア)も、影響を強く受けたのは有名な話。
主人公の三五十五が高校から柔道を始め、僅か2年ちょいで日本一になるというチートストーリー。
作者の小林まことさんが柔道経験者という事もあり、柔道の描写が他の柔道漫画の追随を許さない。
『YAWARA!』の浦沢直樹さんも『帯をギュッとね!』の河井克敏さんも経験者らしいですが、柔道シーンの迫力は敵わない。
一流柔道家が読んでも熱中するレベル。
アラフォー以上の柔道経験者のバイブル漫画。
すぎひろが中高生の時に連載。
かの五輪3連覇の 野村忠宏七段(参考:ウィキペディア)も、影響を強く受けたのは有名な話。
主人公の三五十五が高校から柔道を始め、僅か2年ちょいで日本一になるというチートストーリー。
作者の小林まことさんが柔道経験者という事もあり、柔道の描写が他の柔道漫画の追随を許さない。
『YAWARA!』の浦沢直樹さんも『帯をギュッとね!』の河井克敏さんも経験者らしいですが、柔道シーンの迫力は敵わない。
一流柔道家が読んでも熱中するレベル。